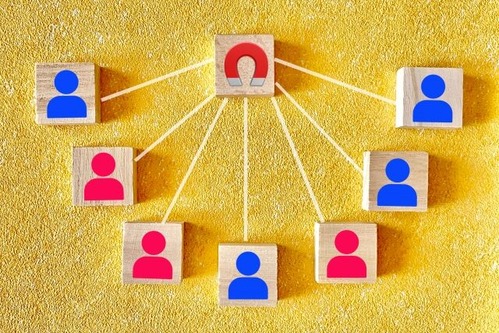2-3年前まで、「炎上」と言えば自社のSNSでの投稿が非難を浴びるなどの事象を指しましたが、最近では消費者が自社の製品に対して事実と異なる発言をしたことの飛び火を受けた処理をする必要が生じるなど、リスクは様々なところに及んでいます。
企業や団体の広報活動は、かつての一方向の情報発信から、社会との双方向コミュニケーションへと根本的に変化していて、この変化の中で広報担当者が対応していくべきは「明確な正解が存在しない複雑な課題群」なのです。
特にデジタルのコミュニケーションにおいては、社会の価値観やルールが急速に変化し、企業はその変化をキャッチアップしながら、時代の空気感も読み取りつつ、自社にとっての正解と調整していく必要があります。
SNSの炎上
初動対応の重要性:
いわゆる「自社ネタの炎上」における対応は、何においてもスピード命とされてきた時代がありました。炎上発生から最初の数時間で、事実関係の迅速な確認と、適切な初期コミュニケーションを、PRコンサルタントが企業に提示していた時期も有りました。
しかし、スピードを重視するあまり不正確な情報や不適切な謝罪を行うことは、かえって炎上を拡大させるリスクがあること、
また、炎上の内容や方法が複雑化していることから、迅速な事実確認を行うことが難しくなっていることは、一般ユーザーにも明らかです。
そのように、一般的にもSNSも炎上ネタは「フェイクかもしれない」「事実確認が必要だ」という常識が定着してきた今は、企業として守るべき価値観と社会的責任を明確にした上で、対応をとることが重要である、必ずしもスピード最優先ではないと認識されています。
対応方針の判断基準:
正当な批判には真摯に対応する一方、理不尽な攻撃には毅然とした態度を示すことも必要であることは、SNSの炎上に限らず、広報の大前提です。
「一貫性を保つこと」を最大の基準にし、法的リスク、ブランド価値への影響、ステークホルダーへの影響を総合的に評価することを原則としてクライアント様に対応をご提示することが多いです。
この「総合的な判断」というのが本当に難しい。クライアントAには適切でも、クライアントBに同じ対応が適切とは限りません。
その意味でも、一般常識的な広報の原則を提示しつつ、その企業に合った最適解を求めるのが最近の炎上事案に必要な対応かと思います。
そのために、我々PRのプロはもちろん、企業の広報も、「社会の常識」「世の中の空気」に敏感であり続けなければなりません。
時に弁護士などの専門家の力を借りることも有りますが、弁護士のような「法律」という絶対的な基準があるわけではない広報の対応は、だからこそ面白いし難しいし、価値があるモノなのです。
コロナ禍における企業広報の役割
この「世の中の空気感」をみることが必要だという考え方は、コロナ禍で一層磨かれたのではないでしょうか。
局所的なものはともかく、広範囲のパンデミックというのは14世紀のペスト流行時くらいしか記録に無く、もちろんその時代の対応が今の時代にマッチしたものでも無く、その都度、企業広報にとって前例のない危機対応が求められました。この時期の広報対応から得られる教訓は、今後の危機管理に活かすべき重要な知見となったと思います。
ステークホルダーコミュニケーションの再構築:
パンデミック初期、多くの企業が従業員、顧客、株主、地域社会といった多様なステークホルダーに対して、統一されたメッセージを発信する必要に迫られました。
この過程で重要だったのは、各ステークホルダーのニーズと関心事を理解し、それぞれに適したトーンと内容でコミュニケーションを行うこと。
誰しもが情報に、その情報の表現に、センシティブになっている日常で、どのようなメッセージをどんなトーンでどのタイミングで発するか。
私どもも、クライアントの競合他社の動向をみながら、その企業の規模感や顧客層などに応じて、対応のご提案をしていきました。
社会的責任の実践:
特に、企業の社会的責任がより強く問われるようになったのもコロナがきっかけかもしれません。
単に事業継続を図るだけでなく、医療従事者への支援、雇用維持、地域経済への貢献など、企業として何ができるかを積極的に実行し、誠実な態度で発信し続けることが評価された時期でもありました。この際、表面的な善意のアピールではなく、本業を通じた実質的な貢献を示すことがいかに大事か、逆のことをすると即マイナス広報に繋がることも、明らかになる社会が形成されたきっかけともいえるでしょう。
デジタルコミュニケーションの加速:
物理的な接触が制限される中、デジタルチャネルを通じたコミュニケーションの重要性が飛躍的に高まり、実際にデジタルコミュニケ―ションを避けてきた私どものクライアントも、従来の広報手法に加えて、その活用法を一考するようになりました。
デジタルだから出来ることが明確になった一方で、アナログなコミュニケーションでしかできない広報活動の重要性も、明らかになったと言えると思います。
広報手法の幅が広がったことは、コロナ禍がもたらした良い面でもあります。
メディア出稿判断:フジテレビを例として
広報が次々と生じる新たな課題を解決しなければならないと感じさせられた事例として、「特定のメディアへの出稿判断」が今年の新たな課題です。フジテレビを例に、出稿判断の考え方を整理します。
多角的な評価軸の設定:
メディア出稿の判断では、視聴率や到達範囲といった従来の指標に加えて、ブランドセーフティ、企業価値との適合性、長期的なブランドイメージへの影響を総合的に評価する必要があります。特定の番組や報道姿勢が自社のブランド価値と相反する場合、短期的な露出効果よりも長期的なブランド毀損のリスクを重視すべきという、少なくともテレビCMでは初めての認識が生まれました。
継続的なモニタリング体制:
メディアの報道内容や番組制作方針は常に変化しています。最近では特定の週刊誌の廃刊を求めるハッシュタグが生じるなど、一読者、一個人がその主張を簡単に自由に行えるようになっているからです。一度の判断で永続的に決定するのではなく、定期的にメディアの動向を評価し、自社の出稿方針を見直す仕組みが必要になります。この際、社内外の多様な視点を取り入れ、偏った判断を避けるようにしなくてはなりません。
代替メディア戦略:
特定のメディアへの出稿を見合わせる場合、その分のメディア予算をどのように配分するかも重要な戦略判断です。デジタルメディア、他のテレビ局、専門メディアなど、多様な選択肢の中から最適なメディアミックスを構築する必要があると言えます。
新しいルールへの適応力とは
現代の企業広報に求められるのは、変化する社会のルールを敏感に察知し、それに適応する能力です。
絶対的な価値基準がなく、ESGやダイバーシティ、プライバシー保護など、新しい価値観が次々と生まれる中で、企業は自社の姿勢を明確にし、一貫したメッセージを発信し続ける必要があると言えます。
変化に対応する柔軟性を持ちながらも、企業としての核となる価値観は一貫して保持することが求められます。私どもPRコンサルタントは、企業の核はクライアント様に委ねるしかありません。その核を求め続ける姿勢こそが、適応力に繋がります。