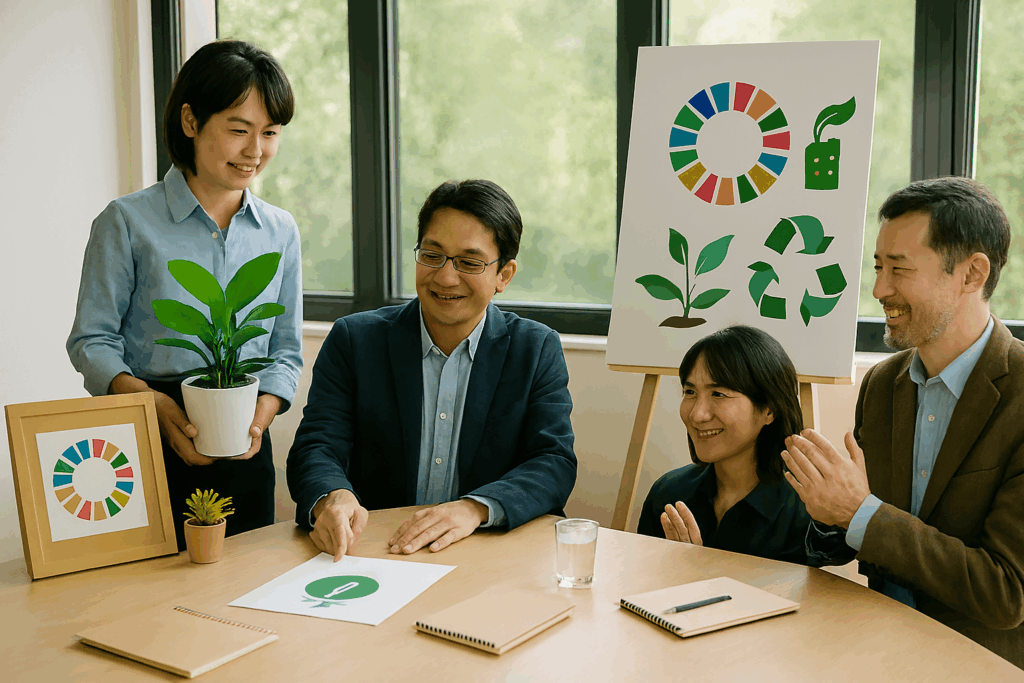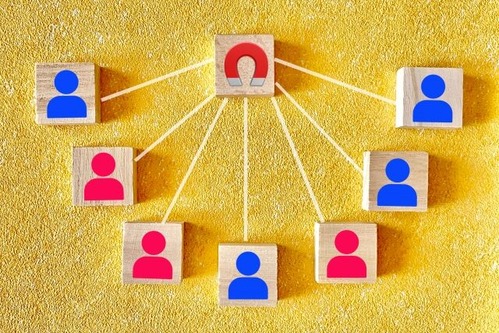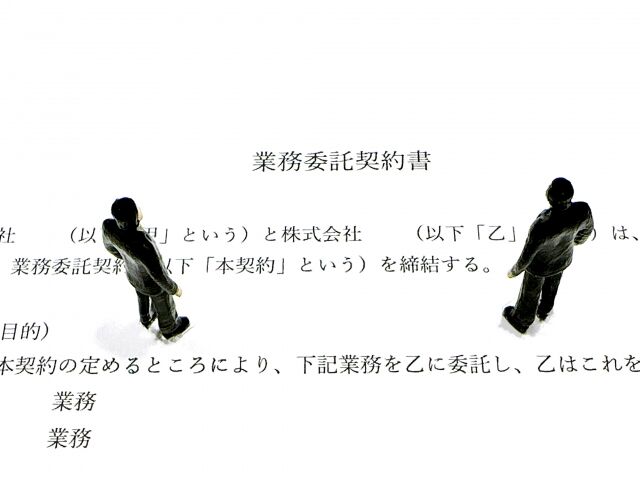毎年9月末の国連総会の会期と合わせた1週間は、持続可能な開発目標(SDGs)の推進と達成に向けて意識を高め、行動を喚起する「SDGs週間(グローバル・ゴールズ・ウィーク)」 として、世界的に注目される期間です。2025年は、9月20日(土)から26日(金)の1週間が予定されています。
今ではテレビ局でも通年で取り上げられるようになったSDGsですが、2020年頃から、この秋の「SDGs週間」と春の「みんなで考えるSDGsの日」に合わせせて春と秋に強化されるようになりました。日本テレビの「#グップラ」は5月のGW終わりが基本ですが、TBSは春と秋に「地球を笑顔にするWEEK」を実施していますし、テレビ朝日も3月と9月に「未来をここからプロジェクト×SDGs」を実施しています。
この絶好のタイミングでメディアに取り上げられるには、直前になって情報発信するのでは間に合いません。今から戦略的なアプローチが不可欠です。
本業とSDGsの明確な接続性
広報活動および企業としてSDGsに取り組む場合、本業との接続性がもっとも大切な部分となります。本業と繋がりのある活動であれば、メディアも取材しやすく、単なる社会貢献活動ではなく、企業の核となる事業とSDGsがどう結びついているかを具体的に示すことが重要です。
具体的な数値・成果の明示
メディアが注目するのは、抽象的な理念ではなく具体的な成果です。CO₂削減量、リサイクル率、社会への影響度など、定量的な数値で活動の効果を示すことが必須です。
この一年間、または直近で発表した社内の数字を今一度さらってみましょう。具体的数値で表せる項目で、成果を示せるようにしておきましょう。
ステークホルダーとの協働ストーリー
SDGs達成のためには、あらゆるステークホルダーとの協働が不可欠 であり、企業単独の取り組みよりも、パートナーシップによる活動の方がメディアの関心を引きます。自治体、NGOとの連携は、社会性の高い団体とのプロジェクトとしてよりメディアが取り上げる意義を見出してもらうことができます。
また、他企業との連携プロジェクトは、「画作り」としてもメディアにとって魅力的です。
このように、協働ストーリーは、より大きな社会的インパクトとして報道される傾向があります。
未来への継続性と拡張性
短期的な活動ではなく、2030年のSDGs達成目標に向けた長期的なロードマップを示すことが重要です。現在、2030年に向けた世界のSDGs進捗状況はわずか16%という現状を踏まえ、自社の取組みが都のように社会課題解決に貢献し、将来的にスケールアップしていくのか、明確に描く必要があります。
この展望を表現できない企業は多いと思います。責任が生じる発言で、他部署の上長の確認が必要だったり、全社的な承認が必要だったり…
明確に言えなくても、展望を可能な範囲で“作文”しておくことが必要です。
タイムリーな情報発信とメディアリレーション
SDGs週間には多くの企業がプレスリリースを配信し、大型イベントも開催されるため、情報の差別化が必要です。週間開始前の事前情報提供や、独自の切り口での情報発信を心がけ、SDGs専門メディアや「サステナビリティに特化したメディアとの関係構築も重要です。
テレビ局のようなメディアは報道番組を中心に取材先を探しています。先んじて9月までのロードマップを描いて、今から自社の活動の内々の情報提供を勧めることも重要です。
SDGs週間は年に一度の絶好の機会ですが、多くの企業が同様の発信を行うため、差別化が不可欠です。本業との接続性、具体的成果、パートナーシップ、継続性、戦略的な情報発信の5要素を軸に、自社独自のSDGsストーリーを構築し、早急に準備を進めることが成功の鍵となるでしょう。再試行
SDGs週間は年に一度の絶好の機会ですが、多くの企業が同様の発信を行うため、差別化が不可欠です。本業との接続性、具体的成果、パートナーシップ、継続性、戦略的な情報発信の5要素を軸に、自社独自のSDGsストーリーを構築し、早急に準備を進めることが成功の鍵となります。